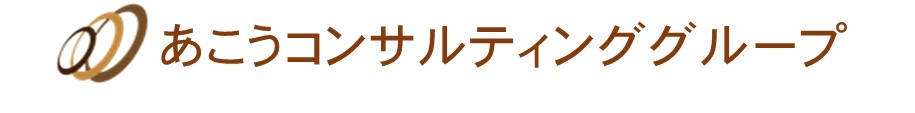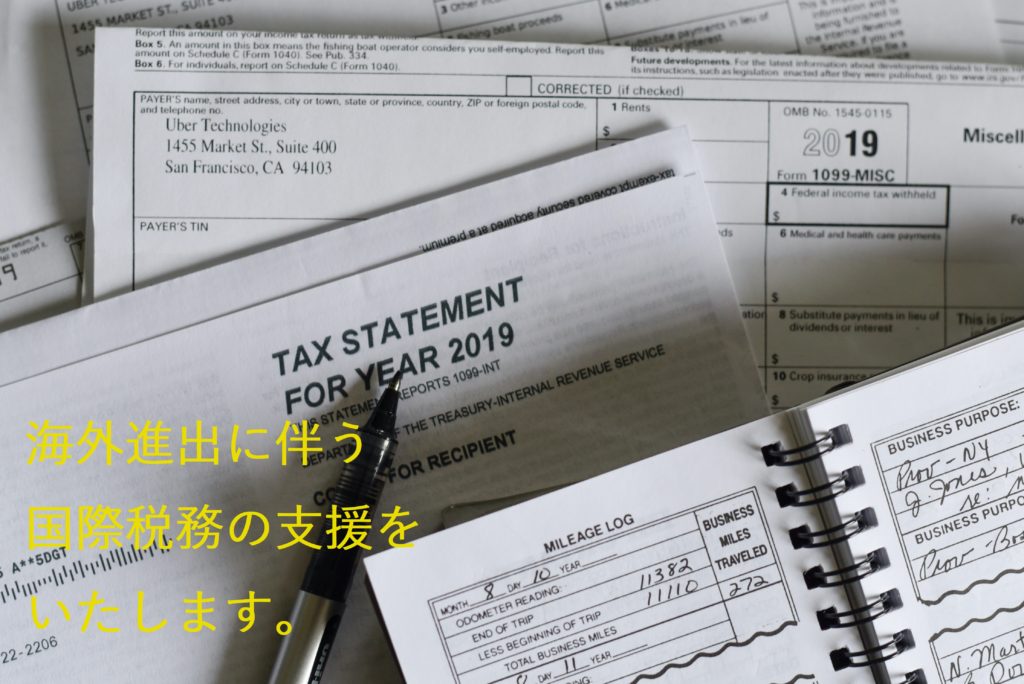
海外進出に伴う国際税務
企業が国外に現地法人(以下、子会社という)を設立しその子会社と取引を行えば、関税・移転価格税制・海外寄付金などの国際課税制度への対応が必要となります。特に移転価格税制による課税は税額が巨額になりやすく、海外進出する企業が最も留意すべき税制です。
移転価格税制とは
移転価格税制とは、例えば、日本の親会社が海外子会社と取引を行う際に、その取引価格(以下、国際移転価格と称す)が資本関係のない独立企業との取引価格(以下、独立企業間価格と称す)と異なる場合、独立企業間価格で取引を行ったとみなして法人税の計算することを義務づける制度です。すなわち、親会社が子会社に1個1,000円で製品を販売したとしても、その製品を独立第三者に1,200円で販売していれば、法人税の計算上は子会社に対しても1個1,200円で販売したとみなして法人税を計算することが要求されているのです。そしてその対象は部品・製品などの有形資産、製造・営業ノウハウなどの無形資産、サービスなどの役務提供、親子ローンの利息とほぼすべての取引に及びます。日本側で移転価格課税がなされた場合、海外子会社の所在国が日本との租税条約締結国であれば、相互協議を通じて子会社側で税金の還付を申請することが制度上認められています。しかし、協議が成立するには多くの時間とコストを要し、協議が成立せず結果的に二重課税となることも多い点が当該税制の問題点として指摘されています。
国際移転価格方針と文書化
移転価格課税のリスクを最小化するための第1ステップは、二つの移転価格方針を決めておくことです。その一つは外部移転価格方針と称し、大きくは6種類ある独立企業間価格算定法の中から自社にとって最も妥当性の高い算定法を選択することです。もう一つは内部移転価格方針と称し、グループ内取引における国際移転価格の設定方針そのものです。
例えば、①親会社から子会社への輸出部品の原価には、製造間接費をどこまで配賦しマージンを何%上乗せして移転価格とするのか、②製品取引であれば海外子会社側の販売マージンを最終製品売価に対して何%に設定するのか、③設計図面の使用許諾を通じた技術ノウハウの提供であればロイヤリティを製品価格の何%に設定するのか、④製品開発上の支援を伴う設計図面の使用許諾を行った場合、開発支援は独立した役務提供取引として費用請求するのか、無形資産取引に包含される行為とみなしロイヤリティの一部とするのか、といった意思決定問題について社内的な方針を決めておくことです。
そして、第2のステップは、ある一定以上の事業規模の企業に対して作成が義務づけられている移転価格の文書化に対応しておくことです。
移転価格文書とは、企業の国際移転価格方針を記述すると同時に、親子間取引を通じた国外への所得移転の発生有無を企業にセルフチェックさせることを目的とする文書です。
海外寄付金
海外子会社を持つ企業が留意すべきもう一つの税制は、海外寄付金です。移転価格税制も海外寄附金も課税対象とする取引は同じですが課税の判定基準が異なります。移転価格税制が実際の国際移転価格とあるべき価格としての独立企業間価格とのギャップを問題とするのに対し、海外寄附金は民法上の贈与契約が成立しているか否かを問題にします。例えば、業績の悪い子会社に対する輸出部品の取引価格を特例的に下げた場合、背景に子会社の業績支援についての親子間の合意があると見なされると寄附金認定のリスクが高まります。このリスクを回避するには、子会社の業績支援が目的ではなく、市場戦略的な経済合理性に基づく価格改定であることを証明する必要があります。
戦略的な国際移転価格の設定
いかなる企業も移転価格課税や海外寄付金による不必要な税金コストは回避したいはずです。しかし一方で、課税を恐れるあまり親会社側のリスク低減のみを意識し、ビジネス上の国際戦略を阻害するような国際移転価格の設定、あるいは海外子会社の利益向上意欲を著しく阻害するような国際移転価格の設定を行えば、長期的にはグループとしての国際経営に負の影響を与えることでしょう。
あこうでは、国際課税リスクの低減と国際経営戦略の双方を視野にいれ、クライアント企業様に最適な移転価格設定方針の立案と文書化対応のお手伝いをいたします。